真実一郎(しんじつ いちろう)さんは、サラリーマン漫画研究家、ライター、そしてパチ怪獣ソフビのコレクターとして多彩な活動を展開しています。
彼の経歴や活動内容、そしてパチ怪獣に見るソフビ文化について詳しくご紹介します。
真実一郎の経歴と活動

真実一郎さんは、現役のサラリーマンとして働きながら、ライターとしても活躍しています。
彼は世相分析やグラビアアイドル論など、幅広いテーマで執筆を行い、多くのメディアに寄稿しています。
特に注目すべきは、サラリーマン漫画の研究です。
彼の著書『サラリーマン漫画の戦後史』(2010年、洋泉社)は、戦後のサラリーマン漫画を通じて、日本の労働文化や社会の変遷を深く掘り下げています。
この著作は、サラリーマンという存在の現在、過去、未来を考察する上で貴重な資料となっています。
また、2018年には市川市文学ミュージアムで開催された「サラリーマン漫画展」の監修を務め、サラリーマン漫画の魅力を広く伝える活動を行いました。
パチ怪獣ソフビのコレクションとソフビ文化

真実一郎さんは、パチ怪獣ソフビのコレクターとしても知られています。
パチ怪獣とは、正式なライセンスを受けていない、いわゆる「パチモン」の怪獣ソフビを指します。
これらのソフビは、独特のデザインや色彩で、多くのコレクターから注目を集めています。
ソフビ(ソフトビニール人形)は、日本で発祥・発展した文化であり、その元祖は1966年に作られた怪獣ソフビとされています。
当時、玩具メーカーのマルサンが『ウルトラQ』の怪獣ソフビを発売し、大ヒットとなりました。
その後、1970年代にはブルマァクやバンダイなどのメーカーからも多くのソフビが発売され、子供たちの間で広く親しまれました。
1980年代以降、中古ソフビにヴィンテージ価値が生まれ、コレクターが増加。
1990年には、M1号というメーカーがレトロソフビを少数発売したことをきっかけに、個人や小規模メーカーがソフビを制作・発売する流れが生まれました。
ソフビは小ロットから生産でき、塗装のバリエーションも作りやすいため、個人が作家性の高い作品を少量生産するフォーマットに適していたのです。
先週末は上海のCrisis Gallery を訪問。僕が提供したヴィンテージ・パチ怪獣ソフビの展示会で、中国の若いコレクター達と議論を交わし、とても刺激を受けた。中国の20-30代は最近5-6年でソフビを集め始めたばかりなので、これから新しいクリエイターもどんどん出てくるのでは。 pic.twitter.com/pyfUeCDwZr
— 真実一郎 (@shinjitsuichiro) October 16, 2024
真実一郎さんは、こうしたソフビ文化の研究や開発にも携わり、noteやX(旧Twitter)などのソーシャルメディアを通じて情報を発信しています。
本日はガメラの日 pic.twitter.com/MLDoeBWQte
— 真実一郎 (@shinjitsuichiro) November 27, 2024
まとめ
真実一郎さんは、サラリーマン漫画の研究やパチ怪獣ソフビのコレクションを通じて、日本のポップカルチャーや労働文化の深い理解と洞察を提供しています。
彼の多彩な活動は、現代社会を多角的に捉える上で貴重な視点を提供しており、今後の活躍にも大いに期待が寄せられています。
彼の活動に興味を持たれた方は、ぜひ彼の著書やソーシャルメディアをチェックしてみてください。
そこには、サラリーマン漫画やソフビ文化に関する深い洞察や最新情報が満載です。
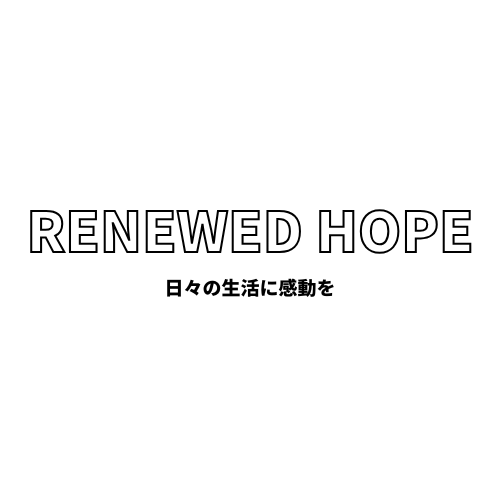

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44a92f53.748e4413.44a92f54.4aa8b417/?me_id=1309253&item_id=12957817&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooksupply%2Fcabinet%2F04216212%2F450%2F9784862485588.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


